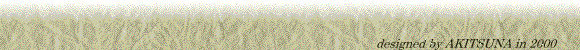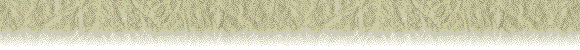 中学・高校生のページ解説 |
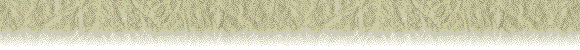 中学・高校生のページ解説 |

|
王子田楽は芸能の区分けのなかでは「田楽躍り」と いう部門に入ります。田遊びや田ばやし、とは異ります。王子神社田楽舞、王子田楽躍り、王子田楽、と 呼び方はいろいろあるけれど同じことです。ようするに王子神社の夏の大祭に演じられる伝統の田楽のことです。 |
以下、文中に「田楽」とあるは特に説明無き場合、田楽「躍り」のこととします。 |
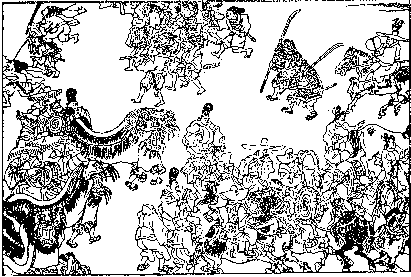
芸能の基本楽器なのです |
王子神社のお祭りでの田楽躍りは、 ごく近世になって田楽舞とも呼ばれるようにもなりました[→王子神社田楽舞]。この地域に伝わる田楽という意味では 「王子の田楽」とか「王子田楽」と言います。 |
| [王子神社の田楽の起源] |
王子神社の田楽は、 その芸態(芸の形とかのあり様)とか王子 神社の歴史とかから考えて、南北朝時代[参考・後醍醐天皇,在位1318〜1339年]前後に始まったので はないかと思われます。 |
[ 田楽(躍り)という芸能の特徴 ] |
田楽(躍り)という芸能の特徴は、 複数のおどり手が笛や太鼓に合わせて鼓やササラや小太鼓を持って、二列になったり、輪になったり、入れ違った りしておどるというところに有ります。そして、最大の特徴は、なんといっても、木あるいは竹を数十枚つづったササラ (筰)という楽器を持つことです。 |
[田あそび、など] |
田遊びや、田ばやし(はやし田) でも、ササラ」とよぶ同じ名前の楽器を使います。でも、こちらの 「ササラ」は田楽(「田楽躍り」とよばれるものの系統)で使うのとはまったく別のものなのです ( どんな形のものなのでしょう。 インターネットや図書館で調べてみてください。) |
[王子神社の田楽の貴重なわけ] |
田楽躍りは今では全国にわずか五十ほどの所 にしか伝わっていないとされるほど貴重な芸能となってしまいました。 |
[王子神社田楽式〈武者の儀礼及び七度半(しちどはん)の儀礼〉とおどりの意味] |
王子田楽をおどる八名の内、 とんがり烏帽子(えぼし)風の花がさをかぶった先頭の二名が『子魔帰(こまがえし)』と呼ばれる神様役で、 平たい花がさをかぶった他の六名がそのお付きの一行(いっこう)ということです。 |
| [日本一美しい王子神社の田楽、日本の文化遺産] |
華美な花がさを付けておどり、田楽の基本型を伝えると言う意味での「形式美」においては 日本一の田楽を自負しております。 |
|